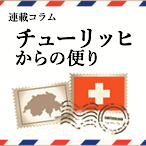『うつ病』(ヴィタリー・ミヌートコ博士著)翻訳から教えられたもの
下中野大人
つい先日、たまたまチェーホフ全集の第14巻(昭和35年初版、51年の再訂版)を開いていたら、付録として、今は亡きなだいなだ先生の小文があった。その中でチェーホフの「六号室」について触れているのだが、一部をそのまま引用させていただきたい。
“この小説の前半に出ている病人の病状の描写なども、鮮やかであり、正確である。教科書に、症例としてのせたら、すばらしい教科書が出来上るだろう。だが、この小説が書かれたのは、精神科の講座が、欧米の大学で、まだ定着してない時代、有名なクレペリンの教科書の第一版すら、まだ出てない時代であったのである。それを考えると、私はチェーホフに脱帽するほかない。”
拙訳『うつ病』の中にも、多くの症例(と言うべきか?)がチェーホフの作品から採られている。それ以外にもトルストイやドストエフスキーといった大御所から、日本人にはあまり知られてない作家の作品、またロシア人の画家、音楽家が登場する。本書の面白いところは、この一点にあると言ってもいいかもしれない。しかし、多くの日本人はふだん触れることのない、あるいは嫌っているかもしれないロシアを、少しでも知ることになるだろう大切な一点、と訳者としては言わせていただく。
著者のミヌートコ先生とは、2009年、モスクワで初めてお会いした。その際、原著をいわばおみやげとして頂いた(先生には、他に統合失調症や、強迫状態—これは500ページ近い大著である—というタイトルの著書がある)。2回目にお目にかかったのは、2013年、第8回国際森田療法学会がモスクワで開催されたときであり、先生は特別森田療法に関心があるという訳でもないのに、私のつたない発表を聞きに来られた。さらには、個人的にプーシキン美術館を案内してくれたり、しゃれたフランス風のレストランで昼食を奢ってくださったりした。これがロシア人気質か、と単純に嬉しかった。このころ既に、ぼちぼち『うつ病」を翻訳していたのだが、このときに、これは何としても日本語にして出さなければ、と心に決めたのである。
話はややとぶが、昨年9月、カンボジアの精神科などを訪れる機会があった。ここでの精神科医療は、貧困と教育問題を背景にして、疾患(特に麻薬中毒患者が目立った)や治療スタイル(僧侶などによる伝統的治療がかなり重んじられている)が、わが国のものとは随分とかけ離れているように見えた。精神科医療の生物‐心理‐社会モデルが言われて久しいが、しみじみ精神科疾患は、患者の置かれた社会・文化的背景に大きく左右されることを思った。グローバライゼーションが広がり、世界を均一化させる方向に文明が進んでいるのも事実だろう。しかし、固有の文化や歴史、伝統などがそう簡単にはなくなるものではない。そうして、患者、いやすべての人はその中で生き、影響を受けているのだ。
そういう意味で、少なくとも臨床にあたる者は、無論自国の文化や社会状況に敏感であるべきだし、ロシアにせよカンボジアにせよ、他国の文化、歴史などにもできるだけ注意を払う必要があるように思われる。それは、医学分野全体からみると、精神科の特殊な事情かもしれない。しかしそれは同時に、精神科医療に携わる者のたのしみでもあろう。
下中野大人(しもなかの ひろと)
医療法人社団翠会 心のクリニック行橋院長。東京外国語大学露語科卒業後,会社勤務を経て,平成2年大分医科大学卒業。九州大学病院精神科神経科,大牟田労災病院,行橋記念病院勤務などを経て,平成17年より現職。著書に,詩集『夕日と狂気』『40人』ほか,小説『我に祝福を』(筆名:神谷和弘),訳書に『うつ病』(ミヌートコ著)がある。
|